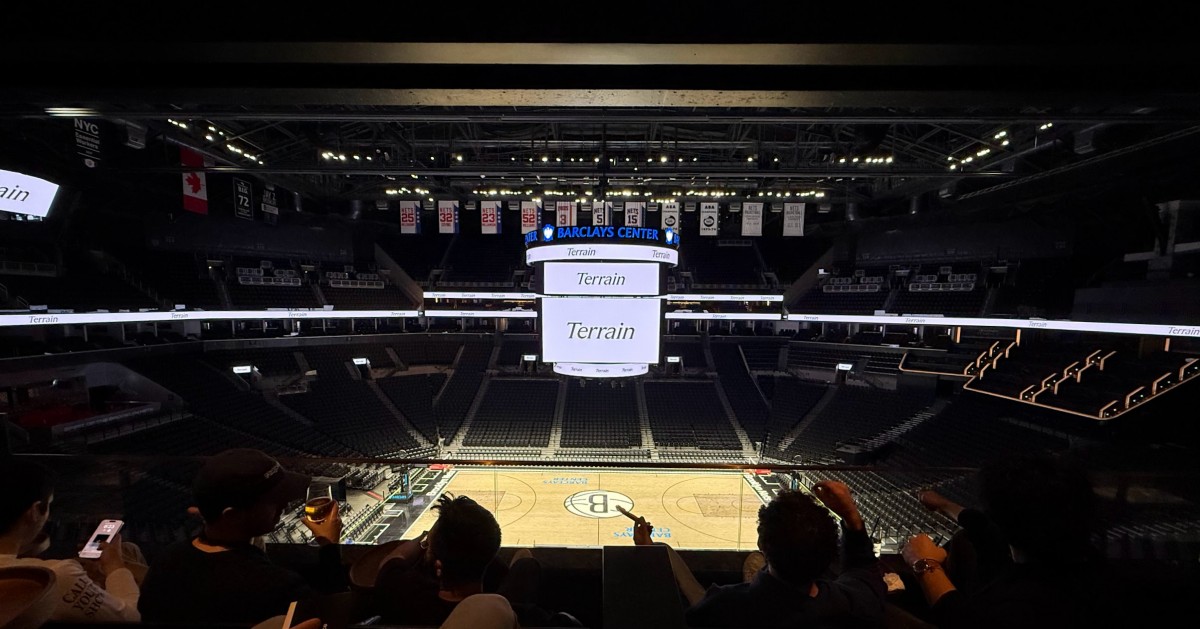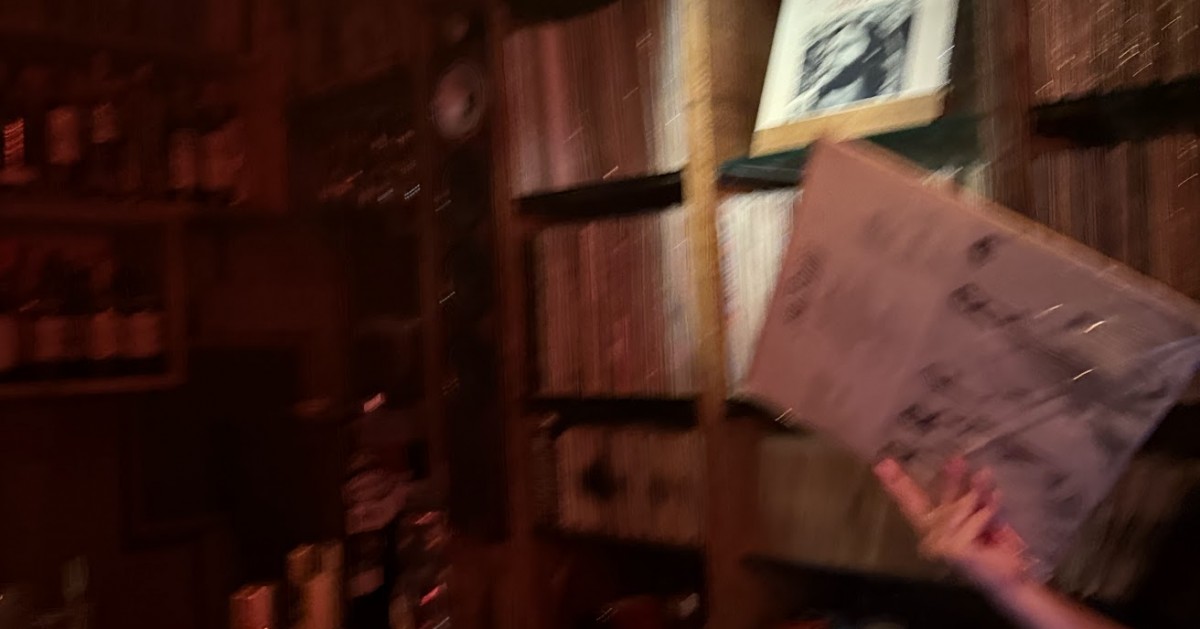#234 アーリステージVCファンド、適切なファンドサイズは?
先週の金曜日(7月4日)は、アメリカの独立記念日でした。この日は誰もが “Happy Fourth of July!” と言い合いながら、お互いにお祝いの言葉を交わします。今回の連休は、イギリス人の友人と一緒に過ごしました。彼女が笑いながら「私にとっては祝う日じゃないけどね」と言っていました。よく考えてみると、この日はアメリカがイギリスから独立した日なので、理論的にはイギリス人にとっては喜べる日ではないのです!
今となっては250年も前の話ですし、こうして笑って語り合える時代になりました。戦争や政治など、国際情勢が不安定な昨今ですが、遠い未来には、最近の出来事も笑いながら語り合える日が来ることを願います。

St. Helena Fire Department
これまで、ベンチャーファンドの規模は成功と直結していると考えられてきました。大型ファンドを運用することが、能力や影響力の指標のように見えるためです。確かに一理ありますが、本当に大きければ大きいほど良いのでしょうか?
初期投資ファンドのサイズを決定する方法は色々ありますが、今回は簡単で直感的な方法をご紹介します。まずはVC自身の投資成功率、いわば「打率」を冷静に評価することです。米国でのベンチャー投資はホームランゲームです。投資20件のうち1件でも成功すれば、打率は5%と言えます。この場合、最低でも20件のポートフォリオが必要になります。2件のホームランを狙うなら40件が必要になります。
投資ペースですが、例えば、投資期間が3年間の場合、この期間に安定的に何件の投資が可能でしょうか?スタートアップのソーシングからデューデリジェンスまで、実際にかかる時間とリソースを考える必要があります。3年間で40件の投資を行うには毎月1件以上の投資が必要であり、これは決して簡単ではありません。20件ならば2ヶ月に1件になり、GPが一人や二人いる場合、より現実的なペースになります。
次に、一件当たりの投資金額、つまり「アロケーション」を検討する必要があります。プレシードからシード段階では、一般的に1件あたり100万ドルから最大500万ドルくらいのラウンドサイズが一般的です。すべての案件でリード投資家になるのは難しく、50万ドル前後のチェックサイズだと実行可能性が比較的に高くまります。このサイズだと、他のリード投資家とシンジケートで共同投資することも可能です。シリーズA段階まで投資を拡大する場合は、もう少し大きな金額を検討できます。
さらに、初回投資後に追加資金を投入するフォローオン投資の比率も重要です。一般的には30%前後が多いです。これに加えて管理報酬やその他ファンド運用コストをそれぞれ年間2%と1%程度で計算すると、10年間で合計約30%の水準になります。
これらを基にファンドサイズを逆算すると、次のようになります:20件のポートフォリオ、各50万ドルの初期投資、30%のフォローオン投資比率、30%の管理報酬などを合算すると、約2,000万ドルというファンドサイズが導き出されます。日本円で約30億円です。
この金額が予想より小さいと感じる方も多いと思います。もちろん、実際にはさらに多くの変数が存在し、ファンド規模を決定するための様々なシミュレーションツールもあります。
ファンド規模が大きくなれば表面的には華やかに見えますが、実際の投資の難易度はむしろ高まります。ファンドの規模が大きくなることによって、投資能力や成功可能性が自動的に上昇するわけでは決してありません。むしろ戦略的なフォーカスが曖昧になり、運用効率が低下するという逆効果が起こる可能性が高まります。
しかし、多くの人がファンドサイズの重要性を軽視しがちな傾向があるのも事実です。重要なのはまさに「適切な」サイズなのです。ファンドサイズも戦略の一部なのです。
すでに登録済みの方は こちら